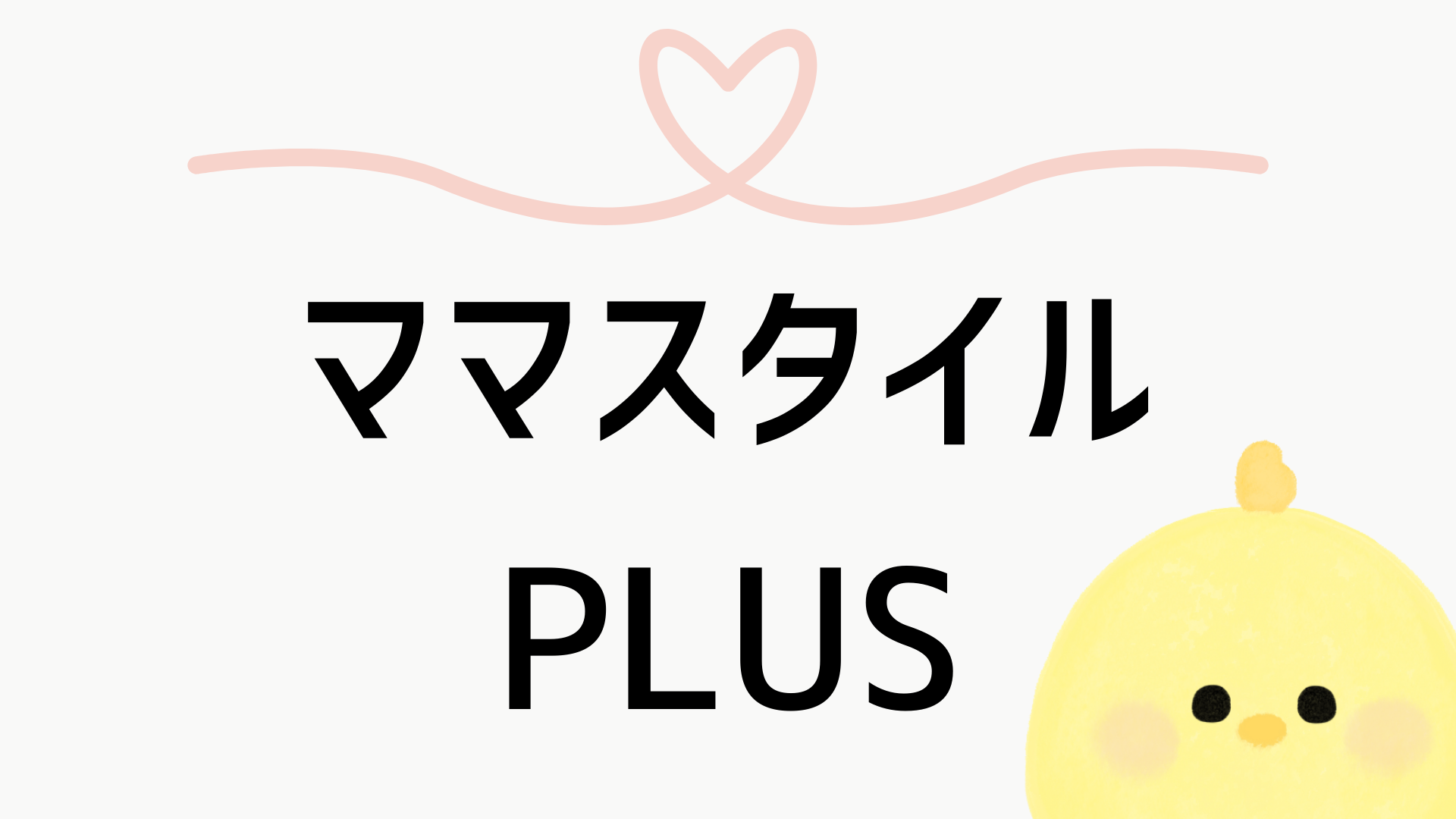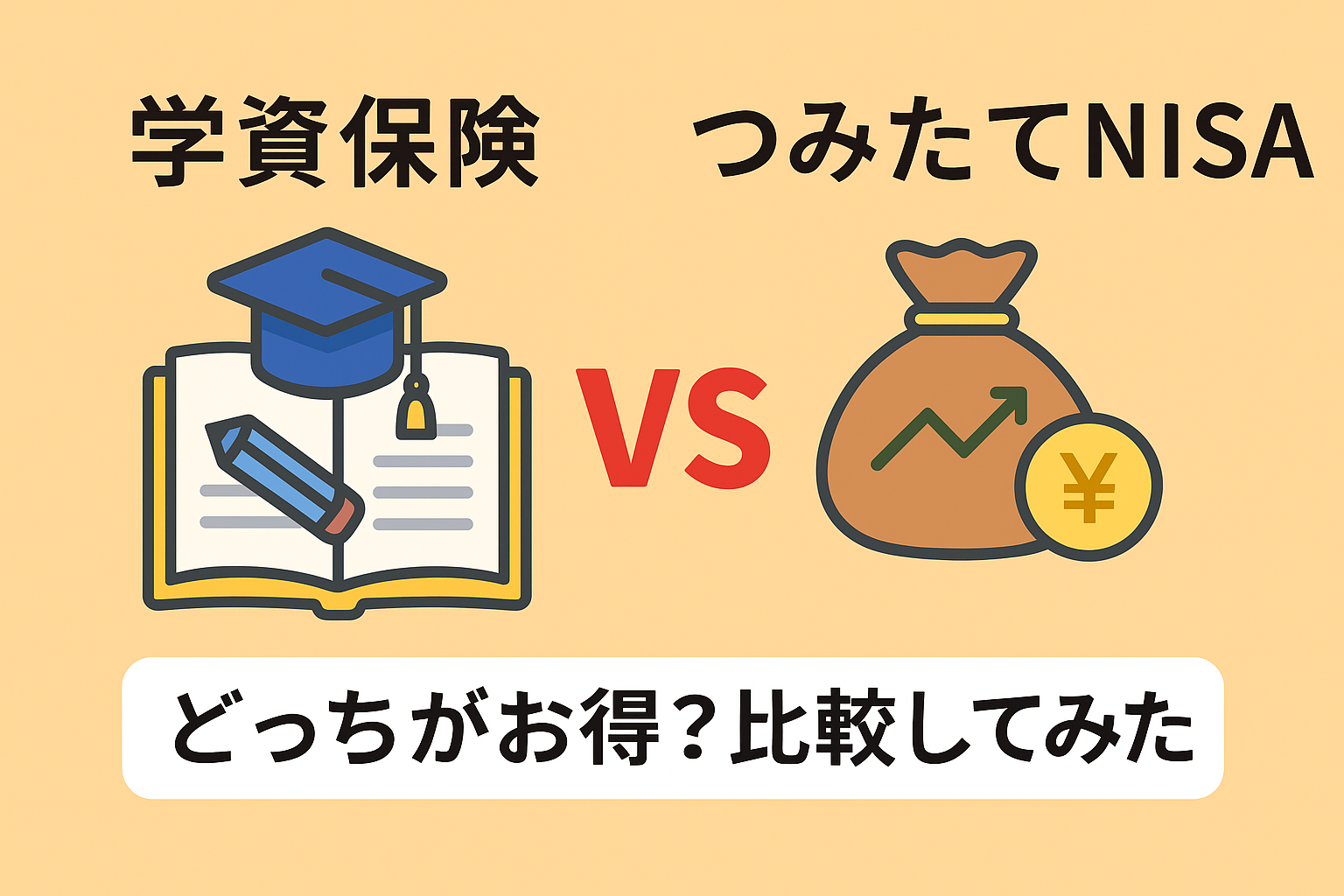みなさま、今日もおつかれさまです。
ひとりひとり生活は違いますが、やることをやっている、それだけですごいことだと思います。
さて、家事や育児に仕事までこなすママ・パパにとって、将来の教育費や老後資金の準備は大きな課題です。
でも、「時間がない」「投資は難しそう」と感じて後回しにしていませんか?
そんな忙しい子育て世帯にこそおすすめなのが、積立NISAです。
この記事では、積立NISAの仕組みから、子育て世帯が無理なく活用できる方法までわかりやすく解説します。
1. 積立NISAとは?

積立NISAは、毎月少額から投資できる制度で、運用益が最長20年間非課税になるのが最大の特徴です。
通常、株や投資信託の利益には約20%の税金がかかりますが、積立NISAならその分をまるごと運用益として受け取れます。
- 年間投資上限:120万円(2024年から新制度)
- 対象商品:金融庁が選定した長期・分散・低コストの投資信託やETF
- 購入方法:毎月一定額を自動で積み立て
ポイント
→ 忙しい家庭でも、一度設定すれば自動で積み立てられるので「ほったらかし投資」が可能。
2. 子育て世帯に向いている理由
① 教育費の準備に最適
教育費はまとまった金額が必要になりますが、数年〜十数年かけてコツコツ貯めることで負担を軽減できます。
積立NISAは長期運用に強いので、子どもの中学・高校進学など先の目標資金づくりにぴったり。
② 少額から無理なく始められる
月1,000円〜可能なので、家計に負担をかけずにスタートできます。
たとえば「児童手当の一部をそのまま積立NISAに回す」などもおすすめ。
③ 放置でも成長が期待できる
忙しい時期に毎日相場をチェックするのは現実的ではありません。
積立NISAなら時間とともに複利効果が働き、資産が着実に育っていきます。
3. 子育て世帯向け積立NISAの活用ステップ
ステップ1:生活防衛資金の確保
まずは生活費3〜6か月分を普通預金で確保。
これがないと、投資中に急な出費があった際に資産を崩さざるを得なくなります。
ステップ2:証券口座の開設
ネット証券(SBI証券・楽天証券など)ならスマホで手続き完結、手数料も安いです。
ステップ3:積立額を設定
無理のない金額から始めましょう。
例:児童手当(月1.5万円)のうち5,000円を積立NISAに回す。
ステップ4:商品を選ぶ
初心者は全世界株式インデックスファンドや米国株式インデックスファンドなど、分散効果が高い低コスト商品がおすすめ。
ステップ5:自動積立を設定
設定後はほぼ放置でOK。年に1回、資産状況を確認します。
4. 積立NISA活用の注意点
- 短期売買はしない
長期でこそ効果を発揮する制度です。値下がりしても慌てて解約しないこと。 - 教育費で使う場合は期限を意識
高校・大学入学前など、使う時期が近づいたら徐々にリスクの低い商品(債券や定期預金)にシフト。 - 投資は余裕資金で
生活費や緊急資金に手をつけない範囲で。
5. モデルケース

ケースA:2歳と5歳の子どもがいる家庭
- 積立額:月10,000円(児童手当から捻出)
- 投資期間:15年(上の子が大学入学まで)
- 年利3%で運用した場合 → 約208万円(元本180万円+運用益28万円)
ケースB:小学生の子ども1人
- 積立額:月5,000円
- 投資期間:10年
- 年利3% → 約69万円(元本60万円+運用益9万円)
まとめ
- 積立NISAは教育費・将来資金づくりにぴったり
- 少額から始められ、忙しくても自動で資産形成が可能
- 長期・分散・低コストの商品を選び、使う時期が近づいたら安全資産へシフト
今日からの行動ステップ
- 生活防衛資金を確保
- ネット証券で積立NISA口座を開設
- 無理のない額で自動積立を設定
小さな一歩が、将来の大きな安心につながります。
今から始めて、子育てと家計にゆとりを持たせましょう。